9月27日、今期のREP(ラグビー・エンパワメント・プロジェクト)の3回目となるオンライン研修が行われました。今回のテーマは「視野をひろげる」。ビジネスとスポーツのフィールドから講師が参加してくださいました。
最初は三菱地所株式会社 広報部コーポレートブランドユニット ユニットリーダー兼ラグビーマーケティング室長である田中文康さんによる「ラグビーと社会とのつながりを考える」。三菱地所と言えば、男女15人制&7人制日本代表のオフィシャルスポンサーも務めるなど、ラグビーをサポートしてくれている会社です。ラグビーとの関わりは日本開催のW杯を翌年に控えた2018年。大会に向け国内の機運を盛り上げようと「丸の内15丁目PROJECT.」を発足させました。実際に「丸の内15丁目」という地名はありませんが、同社が開発を担う東京駅近辺で、ラグビーにちなんだ数多くのイベントを実施。それまであまりラグビーとは馴染のなかったライト層のファンを掘り起こし、翌年のW杯を盛り上げる一翼を担いました。2023年にフランスで開催されたW杯の際は、日本国内をGPS搭載の車で回り、そのルートが「ONE TEAM」を描く「ONE TEAM大作戦」と呼ばれるプロジェクトも実現。同社がラグビーと関わるようになったのは、一般の方々から「スポーツを通した共感」を獲得するため。スポーツを通じたメディア・ブランディングの一環として、ラグビーが選ばれたのでした。
この日も前回の講義同様、参加者からは質問が相次ぎました。「最も反響の大きかった企画は何ですか」「2019年W杯の際、女子受けするために工夫した点は」…。次々と挙手ボタンが押され、田中さんは全ての質問にわかりやすく答えてくださいました。丸の内15丁目PROJECT.では、既に2年後のオーストラリア開催のW杯に向けた様々な企画を準備中とのこと。田中さんのお話は、一般のファンにとっても興味ある内容でした。参加者たちは質問を重ねたことで、より多くの知識を得ることが出来ました。
続いての講師は、元車いすラグビー日本代表の三阪洋行さん。テーマは「ラグビーや社会の多様性について考える」。パラリンピックに選手として3回、コーチで1回出場した三阪さん。その後は日本協会でも安全対策委員会などで活動、10月1日付で日本パラリンピック委員会委員長に就任。日本のパラスポーツ全体を牽引する立場となりました。
大阪出身の三阪さん。高校時代、ラグビー部に所属していましたが、練習中のケガで頸椎を損傷。失意の底から車いすラグビーを知ることで新たな人生の目標を見つけ、NZに留学するなどして努力を重ね、パラリンピックに出場しました。この日、事前に三阪さんから参加者に出されたテーマは「目の不自由な人がラグビーをするために必要なアイデア」というもの。参加者からは「音の出るボールを使う」「レフリーを増やす」「コートを狭くする」…。様々なアイデアの中に「においを使う」というものも。三阪さんも「それは僕も思いつかなかった」。和やかな雰囲気で講義は進みました。ご自身のこれまでの道のりと、車いすラグビーの競技方法について説明、三阪さんから参加者に向け、「皆さんが思う障がいとは何ですか」という問いも。「一つの個性」「出来ないことを強みに変えるもの」…。こちらも様々な答えが返ってきました。最後には、自分の価値観にとらわれないこと。目的地への道は一つではないこと、自分の限界を決めないことなど、三阪さんから参加者に向けたメッセージがあり、それは、これから人生を切り開いていく参加者にとって心強い道しるべでもありました。
前半の講義に引き続き、三阪さんにも質問が相次ぎました。「選手とコーチで気持ちの変化はありますか」「教える立場になって変えたことは」といった内容から「選手時代は、どんな筋トレをしたのですか」といった選手目線の素朴な質問まで多岐にわたりましたが、こちらも分かりやすく答えてくださいました。参加者にとっては、ビジネスフィールドにおけるラグビーの存在、パラスポーツの魅力と、様々な知見を得られた第3回の講義でした。
[参加者の声]
▼全体を通して
「今まではラグビーという一つのスポーツだけでしか見ていなかったが、あまり考えてこなかったもう一つの視点を知ることができた。自分が知らなかった知識を得ることができ、貴重な体験だった」
「全体的に質疑応答が多くて、自分の気づかなかった観点も共有できたことが嬉しかった。個人的なことにはなるが、講義中に常に質問を考えながら内容をインプットしたことで、早い段階から質問できたことが良かったと思う」
▼講義「ラグビーと社会のつながりを考える」
「講義を通して、ラグビーが単なるスポーツとしてではなく、“街の文化”や“人と人をつなぐきっかけ”として発展していることを知り、とても新鮮に感じました」
「心に残っているのが、“真面目に面白いことをしよう”という言葉。(中略)面白いことをするにはアイデアの引き出しがたくさん必要だと思うから、自分の興味あること以外にも、普段から目を向けてみたい」
▼講義「ラグビーや社会の多様性について考える」
「障がいがあるからといって配慮し過ぎることはスポーツらしさが消える、という意見がこれまで考えたこともなかったので、心に残った。無いものに目を向けるのではなく、あるものに目を向ける視点は、健常者にとっても大切な考えだと感じ、これから意識していきたいと思った」
「車いすラグビーは知っていたが、ルールも知らない状況だったのでこの機会に知れて良かった。女子選手を増やすための取り組みとして。ルールから少し変える取り組みが男女差を感じさせないフェアな競技にできていて、もっと知りたいと思えた」
▼第1回レポートはこちら
▼第2回レポートはこちら

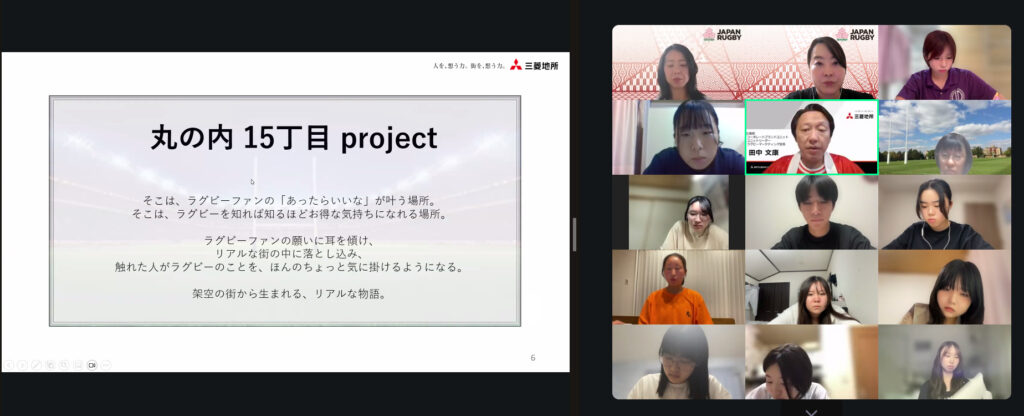


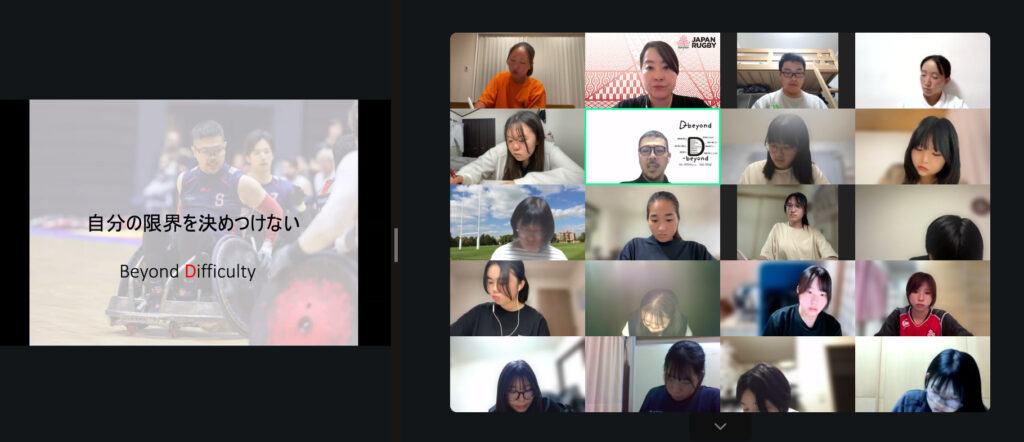

 www.rugby-japan.jp
www.rugby-japan.jp