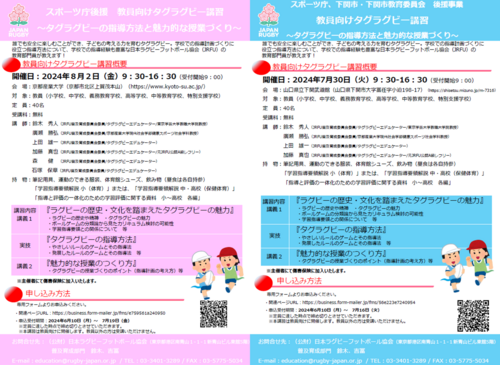|
報告:広島市立段原小学校教諭・北谷一水
広島市小学校教育研究会体育部会
平成21年度夏季体育科・タグラグビー研修会の開催報告
毎年、広島県広島市小学校教育研究会体育部会では、小学校における体育科の指導方法に関して研究を深め、指導力の向上を図ることを目的として、市内の教師を対象に体育実技研修会を開催しております。
去る8月17日(月)残暑厳しい日差しの下、サッカーJ1「広島サンフレッチェ」のホームグランドである広島広域公園(広島ビッグアーチ)において、当体育部会主催による「平成21年度夏季体育科・タグラグビー研修会」が、小学校の教師約100名を集めて開催されました。
 |
|
 |
| 広島県協会神出会長ご挨拶 |
|
研修開始前のウォーミングアップ |
平成23年度から全面実施される「小学校学習指導要領」に、ゲーム・ボール運動領域として「タグラグビー」が例示されたことを受け、今後、体育授業等において子供達を指導する立場に有る小学校教師として、タグラグビーそのもの及び指導方法等を学ぶ意味から、今年度の実技研修会では、初めてタグラグビーを取り上げることになりました。
研修に先立ち、広島県協会・神出亨会長によるご挨拶があり、「子供達の心と体の健全な育成と、タグラグビーをはじめとするスポーツのかかわり合い」を感じながらの実技指導が始まりました。
実技指導には、日本協会・普及育成委員会から派遣された飯原雅和氏、地元広島県在住の関西協会・普及育成委員会・永川信平氏のインストラクターに加え、アシスタントコーチとして広島市立戸坂城山小学校教諭・藤城文浩氏の協力をいただき、3名のコーチ陣による熱心な指導が繰り広げられました。
 |
|
 |
| ロブザネスに興じる教師達 |
|
日本協会・飯原インストラクター |
開始早々、元気いっぱいのコーチ陣の小気味良いリズムに一同圧倒され、自然に体が動き出し、ウォーミングアップには素早い動き・巧みな動き・反射神経を養う動きが盛り込まれ、心地よい汗がにじみ出ておりました。
以下に指導内容を順次紹介して行きます。実際にラグビーボールを使用したゲーム感覚の運動遊びで、7~8人でチームを組み、四隅のコーナーに分かれ中央に転がっている7個のボールを、3個早く集めたチームが勝ちの「ロブザネス」と言ったリレーゲーム。さらにはそこにパスを取り入れ、ボール扱いの巧みさ・スキルアップを狙った指導。仲間や相手の動きを「目で見て、耳で聞いて、声に出す」ことが最も大切との指導を受け、この頃にはほぼ初対面だったチームメイトと喜びを分かち合い、声を掛け合う姿が随所で見られるようになっていました。
指導内容は少しずつラグビー本来の動きに近づいていく。下からそっと優しいパスを出し、パスを受ける相手のことを思いやり、ていねいで捕りやすいボールを投げるにはどうすれば良いか。それに加えてボールのスピードやポジショニングも要求される。年齢も性別も体力もバラバラの仲間達がかかわり合い、お互いにアドバイスし合い試行錯誤している。ここでも、いつの間にかチームメイトを思いやる言動・仕草が多く見られるようになっていました。
 |
|
 |
| 丁寧なパスを心掛け |
|
タグの試合・1 |
指導の最後、実戦形式の試合になるとチームの団結はより一層強くなり、大人達が本気で走り、夢中でボールを追いかけ、良いプレーには自然にハイタッチやガッツポーズが出るようになっておりました。
完全にルールを理解していなくても、思うように動けなくても、皆若干の疲労は感じつつも満足そうな笑顔で、初体験であるタグラグビーの実技研修会は無事終了することが出来ました。
実際にタグラグビーを指導体験してみて、このスポーツには何種類もの楽しさが詰まっていることを実感しました。技術の向上はもちろん、作戦を練るアイデアや仲間とのかかわり合い、そして充実した達成感ではないかと感じました。
体育科ならずとも、教師の側がこうした狙いや明確な意図を持って授業づくりを行うことは、最も基本的で大切なことであると同時に、ここで培う体力や人間関係は、日々の生活にも大いに役立ち、友達を認め合い、心を豊かにすることに気が付きました。
運動は楽しくすること。指示は短く分かりやすく。声を掛け合い認め合うこと。子供達に対してタグラグビーを指導する前に、この貴重な経験ができたことは、楽しさを伝える何よりの近道であったように思われ、タグラグビーとは、何とも不思議な力を持ったスポーツであると強く感じた一日でした。
 |
|
 |
| タグの試合・2 |
|
タグの試合・3 |
|