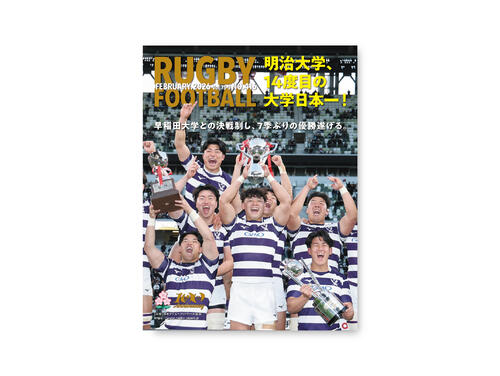|
公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団と日本ラグビー協会が主催する「みなとスポーツフォーラム 2019年ラグビーワールドカップに向けて」の第36回が9月30日、東京都・麻布区民センターで開催され、元NHK解説委員で法政大学スポーツ健康学部教授の山本浩氏が「2020東京オリンピック・パラリンピック招致活動を振り返る」をテーマに講演した。
山本教授は「きのうの晩、招致関係の方たちとぶどう酒を飲みながら話を聞いたんですが…」と切り出すと、知られていない“裏話”などを、元アナウンサーならではの軽妙なトークを交えながら展開。その興味深い内容にフォーラム参加者からは時に驚きの声が上がり、時には大きな笑いが起きるなど、五輪招致活動の裏側がうかがい知れる有意義な1時間の講演となった。
■投票が9月4日だったら東京の招致はなかった
|
![山本浩氏]() |
|
|
山本浩氏
|
五輪の招致活動には、「メディア戦略」「世論戦略」「IOC戦略」の3本柱がある。東京都は、コンパクトな施設配置やテクノロジー、震災復興、おもてなし精神などを訴えかけていった。しかし、投票の直前になって、「訴えかけたすべての言葉に雲がかかってしまった」(山本教授)のが汚染水問題だったという。
「きのう、ある幹部がこう言っていました。9月4日に投票が行われていたならば、東京の招致成功はなかっただろう、と。4日の段階というのはすべてのメディアがおしなべて汚染水の問題を取り上げている時期で、CNN、NBC、ニューヨークタイムズといった世界のテレビ、新聞が上から3項目くらいまでに伝えるニュースでした」
しかし、投票前日の6日には「G20」が世界のトップニュースに躍り出ます。東京への逆風が弱まった中で投票は行われたのです。結果はご存知のとおり2020年五輪開催地は東京に決定。
東京をはじめ、マドリード、イスタンブール、それぞれの都市に弱み・強みがあった中で、東京が選ばれた勝因には『総力』が挙げられると山本教授は語る。
「『総力』とはなにかと言いますと、世論、競技団体、さらには経済界、そして政官界、これらが一緒になって歩みをそろえながら前へ進んだこと。これを『総力』と言います」
その中でも山本教授が注目したのが世論の力だ。これらを『自力』とするならば、『他力』というものもある。『他力』というのは他の都市の抱える不安要素のうち、票を東京に切り換えさせる要因になった案件だ。
例えばイスタンブールなら反政府運動の高まり。「アジアと欧州の架け橋になると言いながら、市民の間に橋をかけられなかった」ことや、頻発したドーピング事例。マドリードでは、失業率27%に見られる財政危機だ。投票直前の8月下旬に山本教授は実際にマドリードを訪れており、そこで見た「あまりに安い招致活動の展示」に驚いたという。
また、ここで興味深い話も飛び出した。「IOC委員が入れる票のおよそ5分の1ぐらいは、その委員の奥さんや旦那さんが決めていると、まことしやかに伝えられている」というのだ。IOC委員の妻や夫でスポーツにあまり関心がない人がいたとする。そうした人の中には、五輪開催中にショッピングが楽しめる街なのか、歴史的・芸術的価値のある建造物が豊かな都市なのかを大切にすることがあるというのだ。五輪とは別の部分で魅力ある都市かどうか。そこに力点を置いて票が投じられることもあるとなれば、「必ずしも節約型の五輪がIOC委員の方々すべての気持ちに沿うということでもない」と、山本教授は指摘している。
さらに、マドリードが抱えた問題として、イギリスとスペインの間で領有権の争いがある「ジブラルタル問題」も挙げていた。
■IOC委員の投票行動には『総論』と『各論』がある
ライバル都市もそれぞれ問題を抱える中、東京は世論にもIOCにも大きな影響を与えた汚染水問題を背負って投票の期日を迎えるわけだが、いざ投票となるとIOC委員の行動に訴えかけるものには『総論』と『各論』があると、山本教授は説明する。
「『総論』というのは、理想の五輪を開催するためにはどの都市が選ばれるべきなのかという判断によるもの。一方で『各論』というのは、利益ベースで考えるとわかり易い。「この都市で開催されることが帰属組織(国や所属団体)の意向に沿う・利益をもたらす」ものを『各論I』とするならば、『各論II』という、「この都市に入れることが自分の利益にかなっているかどうか」を大切にしたやや狭い考え方もある。「例えばある国際競技団体の専務理事だったとしますと、自分たちの国際競技団体にプラスになるかどうかを判断して票を投じる場合は『各論I』に従うことになりますし、自分の家族にとってこの都市の方が都合が良いとなれば、『各論II』を考えた投票と見ることができる。大きく分けて、『総論』で投票するのか、『各論I』なのか『各論II』なのか、IOC委員のそれぞれがそれぞれの見識で投票することになっているわけです」
こうした視点に立って今回の投票をみれば、総論で票を投じた委員が多かったのではないかというのが招致活動に当たった人たちの感触だ。ただし、投票は無記名で絶対の秘密。実際のところ各委員がどのような理由でどの都市に投票したかは、「はっきりしないのが招致活動の実態なんです」と山本教授は付け加えた。
■2016年の敗退の経験を生かした周到な招致活動
IOCは、五輪立候補都市に何を求めたのか。「その都市で五輪が開催されることで、五輪がどう発展し変化するか。逆に、五輪を開催することでその都市がどう発展し変化するか」を示せ。3都市に直接突きつけられた文言ではないが、現在のIOCは取り巻く競技団体にも同じような投げかけをくり返している。五輪と団体・組織とがお互いに発展・繁栄できるのかを重視する時代になっているのだ。
「実は東京都が立候補するときに、頭をひねったのがこの部分でした。『理念』といわれるものがそれでしたが、つまり東京が五輪を開催することで五輪になにをもたらすのか、一方で東京は何が変われるのかを端的に表す言葉を示すことでした」と、山本教授は明かす。
これを3つの都市に当てはめると、それぞれの凹凸が浮き上がってくる。マドリードの場合は五輪を開催することで財政再建が見込めるが、五輪がどう変わっていくのかが見えていなかった。イスタンブールの場合はアジアと欧州をつなぐことができる、世界での認知度を勝ち取ることができると、両方ともそれなりの答えを持っていた。
それでは東京はどうだったか?
「質の高い競技運営で五輪の商品価値を高めるという経済面での強みを前面に出し、一方で東京、ひいては日本は景気の回復と震災復興が見込める、というように明確に整理されていました」。国内のメディアには、説得力の強いメッセージには見えなかったようですが、IOCに対しては十分だったのです。
また、2016年の敗退の経験を生かし、今回は周到な招致活動が行われていたと、山本教授は説明する。その中には「計算もあったが、『偶然』の力もあった」という。『偶然』のひとつがロンドン五輪での日本人選手の活躍。メダリストによる銀座パレードは予想を大きく上回る50万人の賑わいで、世論が東京招致に一気に傾いた。この“熱”を冷まさないように、招致委員は常にキャンペーンを打ち続けた。
そしてもうひとつ、招致活動にとって大きな力となったと山本教授が強調するのが、平成23年8月に施行された『スポーツ基本法』だ。
「この基本法ができたことで、国も腰を上げることができたわけです。総力をあげる意味でも大きなバックグラウンドになりました。国が一丸となって動けたその背景に、スポーツ基本法があったことは忘れていただいては困りますね」
この基本法をもとにした政界の動き同様、経済界の働きかけも早く、そしてスポーツ界も東京招致に向けて継続的に活動。これら招致委員の活動の一例として山本教授は、アフリカのIOC委員、中東の重鎮の影響力などを軽妙に紹介し、“票の流れの複雑怪奇”で会場を大いに盛り上げた。
■言葉が人を動かす時代に
2020年東京五輪開催決定により、その前年に日本で開催される2019年ラグビーワールドカップ成功に向けて追い風が吹いた、と語る山本教授。ラグビーW杯、東京五輪で確実な成功を収めるためにも、「スポーツの再評価」「スポーツのコミュニケーション能力」「スポーツのフェアネスを社会全般に持ち込むこと」を高めることを挙げ、競技レベルの強化の観点から「“人を選ぶ”ことが大事な時代になる」と強調する。さらに話は、日本と欧米に見る盲導犬の育成方法の違い、元サッカー日本代表監督のイビチャ・オシム氏の指導方法の例などを挙げ、「個性、すなわち個別の能力をとことん生かす」ために、指導者・選手ともに話す力、聞く力、読み取る力といった“言葉の力”を高めていくことも重要であり、「言葉が人を動かす時代に入った」と山本教授は締めくくった。
■「今回の招致活動は深い配慮のもとで自制の利いた行動だった」
およそ1時間の講演のあと、休憩を挟んでフォーラム参加者との質疑応答に入った。
──メディアでは東京五輪のことを多く取り上げられていますが、ラグビーW杯のことはほとんど取り上げられていません。今後、ラグビーW杯が多く取り上げられるにはどうしたらいいでしょうか?
山本教授「スポーツが多くの人たちの感動を呼ぶ大きな理由のひとつは、そこにいる人たち、あるいはそこでプレーしている人たちが自分と重なっているかどうか、ですね。
例えば我々が幼稚園に行って運動会を見るとします。あたりをみると熟年のご夫妻がいたりする。孫の運動会なんですね。運動会そのものが目当てと言うより、孫の活躍が目当て。見方を変えれば、孫が出ていない運動会に行くおじいちゃん、おばあちゃんはそんなに多くないと思うんですね。自分の孫が出ているときと全然違うんです。例えば、自分の子どもが出ている小学校の運動会でおじいちゃん、おばあちゃんが見に行っているときのかくしゃくとした様子と言ったら…あんなに拳を振り上げなくてもいいじゃないかってくらい応援しているおじいちゃん、おばあちゃんがいたりします。つまり自分の孫と言う、自分の心と一体となっている、つながっている人がいる。そこに大きなエネルギーを引っ張ってくる要素があると思うんです。
スポーツというのは必ずそういうところがあります。例えば自分が応援しているチームは自分が所属している会社だから、あるいは自分が住んでいる町をホームにしているから、といろんな理由があると思うんですが、そのスポーツを応援するときには“一体感”、そこにつながる自分があるかどうかだと思うんです。ラグビーの場合にはそういった要素をいかに外に出していくかだと思います。我々の中のラグビーがここにあるんだということをメディアを通じて日本国内に知ってもらうというひとつのやり方があると思います。そこに“私”がいるというのがスポーツにとって大事なことですから、ラグビーの場合、そういう人たちをどう生かすか。メディアもそういったところを取り上げるべきだと思います」
──東京五輪招致におけるブエノスアイレスでのプレゼンテーションの評価、また裏話などあれば聞かせてください。
山本教授「プレゼンテーションに関しては、安倍総理は現地では3時間くらいしか練習されなかったそうですが、それまでに国内で相当に稽古を積んできたというんですね。日本国内に演説・スピーチ用のアドバイザーがいることはすでに指摘されています。つまり、安倍総理自身、普段から演説のときにもトレーニングしているはずなんですよ。アメリカの大統領が昔からしているのと同じように、演出家がいろいろとアドバイスしている。あのプレゼンテーションも、東京でいろいろとトレーニングを重ねてきたんだろうとみられています。
一番説得力があったと言われているのが高円宮妃殿下ですね。妃殿下はあくまでも日本サッカー協会名誉総裁、あるいは日本ホッケー協会名誉総裁という肩書きで、東日本大震災に対する世界のスポーツ界の励ましに対する感謝の言葉をおっしゃるのが目的だったと言います。そこを意識して、招致関係のメンバーから5メートル離れて歩いておられたそうですね。お召しになっているウェアも違いました。そして、スピーチが終わったらあの場をお立ちになる予定だったんですが、妃殿下は壇上におられたままでした。それが逆に良かったと言われていますね。また、妃殿下はロビー活動という意味でも、IOCの方々に汚染水の問題でいろいろと説明をされたということも伝わっています。
招致活動は緻密にされていたと思いますね。ロビー活動のうち『1票入れてください』という活動はすでにあの段階では終わっているんです。招致関係者のもとにはIOC総会の行われる現地で20行ぐらいにわたるお触れ書きが回されたようです。これをするな、あれをやるなと書いてあって、例えば、廊下で声高にしゃべならい、むやみに電話しない、携帯電話をかけながら歩かない、やたらに握手を求めない、名刺を出してIOC委員と挨拶をかわさない。これをすべて守っていたら何もできないってくらい書いてあったようですが、日本の招致関係者は実に見事に守ったんだそうです。
また、広報担当者もしっかりしていました。メディアが非常に多かったんですけど、ことあるごとにメディアを集めて、何度も細かな要請をしているんです。大集団の日本メディアが、実に整然と取材活動をすすめた。これもまた、間接的に大きかったですね。
ほかにもいくつもあるんですが、そのひとつひとつが結果的に見ますと、かなり深い配慮のもとで自制の利いた行動だったと伝わっています」
──今後、東京五輪に向けて最も変化していくことは何でしょうか?経済なのか、教育なのか、政界なのか、それともスポーツのあり方そのものなのか。
山本教授「私が感じるのは、例えば今の中学生の年代から2020年の段階でいい感じのアスリートが出てくると思います。特に競技によっては、年齢が若くして戦う体操の選手などがあるでしょう。ところが現状ではいくつか問題を抱えています。中学3年生から高校生に行くときに、間にトレーニングの小さなギャップができかねないんです。部活動でやっている選手は、わずかですが練習の中断期間ができます。そのギャップは高校から大学に行くときにもう少し大きな形で出てきます。受験というもので。部活から離れて2カ月、3カ月まったく体を動かさない。進学した後も環境が変わって食生活にも変化が生まれたりする。こういう現状をそのままにしておくのかどうかです。
スポーツ界だけではなく、教育界も巻き込まないと改善できないことです。では一方的にクラブ化してしまうか。すると、体育の先生の部活に対する関わりをどうするか。それらを含めて、ラグビーの問題もそうだと思いますが、年齢別のカテゴリーを考えたときに、年齢別の間の途切れるところを学校教育の中でどうするのかということが、スポーツ界にとっては非常に大きな問題だと思います。
もうひとつは、JOCと日本体育協会が一緒になることを検討することです。スポーツ省ができたとき、そこに対する対抗勢力としてJOCと体育協会がちゃんとモノを言うという風にして、もうひとつこちら側にJSC、日本スポーツ振興センターというお金を出す部分がありますが、JSCとJOC・日本体育協会が一体になった部分と、スポーツ庁なりスポーツ省とがお互いにそれぞれ強い力をもって、道理を言いながら、日本のスポーツ界に対して責任を持ってほしい。そういう時代に来ているんじゃないかと思います。
東京五輪・パラリンピックで障がい者スポーツも入ってくることも大きな変化をもたらすと思いますので、それらを含めて体制の変化を我々の力でどう動かせるかを検討するときが来ているように思いますね」
■なぜJリーグが今、2シーズン制でもめているのか?
──Jリーグやラグビー・トップリーグの人気をどう上げていけばいいか、意見をお願いします。
山本教授「全然関係ない話かもしれませんが、Jリーグは今、2シーズン制の問題ですごくもめているんです。横断幕を掲げて『Jリーグ許さず』みたいなことになっているんですね。なぜこういうことになったかと言いますと、実はですね、あんまり報道されていないことなんですが、日本サッカー協会がもともと秋・春シーズンにしたかったんですね。
なぜ秋・春シーズンにしたかったかと言いますと、日本はワールドカップ出場の決定が世界で一番早いんです。それはアジアの強い国のリーグが春・秋シーズンだからなんです。春・秋シーズンでやっているために、早くワールドカップ出場国を決めないと、もしリーグ優勝が決まる秋にワールドカップ出場権をめぐって選手を代表に引っ張るとなるとクラブの監督やフロントがものすごく困ることになります。秋のリーグ優勝が決まるときにナショナルチームに選手を引っ張られるとリーグが運営できないぞ、ということになるわけです。そこでW杯出場決定を6月にするのはいいんですが、6月にやったらその後の代表チームは、国同士の真剣勝負が1年間ないんです。あとはフレンドリーマッチしかないんです。それじゃ困るから何とかもっと深くまで行ってやりたい、じゃあそのためにどうするかと言いますと、日本サッカー協会は秋・春シーズンにしたいんです。
そうすることによって本田選手や長友選手を呼んだときにも、秋にもしW杯出場が決まるんだったら、彼らはシーズンの最初で元気です。ところが、6月に決定するとなると本田選手も長友選手もヘトヘト。そういうことで本当に戦っていけるのかと考えると、この先難しいと思っているわけです。そういうヨーロッパとの関係でどうするのかと考えたときに、サッカー協会は秋・春シーズンしかないと考えたんです。
ところが、当初Jリーグは反対しました。なぜか? 冬の期間は雪が降ってお客さんが来ない地域がある。これはラグビーの場合も同じです。一方で雪が降ってグラウンドの整備をするときにお金がすごくかかる。そのお金をかけたところに雪がどんどん降ってくる、お客さんが来ない、どうするんですか? じゃあそこは休みにしましょう、冬休みを長くして日程をずらしましょうとなると、今度は水曜日の試合が増えてくるんです。水曜日の夜の試合となるとお客さんが激減しまう。そうすると、入場料を経営の柱のひとつにしているところが途端に経営難に陥るわけですね。こういう悪循環の中で秋・春シーズンは厳しいとなったわけです。
じゃあ、どうするんだ? そこで出てきた折衷案ともいえるのが、この2シーズン制なんです。チャンピオンシップによるスポンサー料、放送権料の獲得も重要ですが、2シーズン制では、他の影響も出てきます。監督の心理を考えてみましょう。これまでもそうでしたし今後もそうでしょうが、欧州のクラブへの移籍を希望する選手がチーム内に生まれたとしましょう。選手の移籍はどうしても欧州クラブの夏休みの時期です。これがJクラブの監督にとっては大きな痛手です。優勝を目指して戦っている最中に、チームのレギュラーメンバーを抜かれてしまう。戦力が整わないうちに、シーズンの後半に突入。計算が合わなくなって順位を落としかねない状況に陥ります。ところが2シーズン制では、状況が違います。第1ステージが終わったところで順位が決まる。第2ステージは新たな体制でもう一度戦えるわけです。どちらのシーズンも監督は計算外の選手の移動が少なくて済むんです。そういう中で戦うのであれば、チームを預かることができる。だから、2シーズン制にして、そこで儲かったお金を今度はJ3に配りましょうということをやるわけです。
日本サッカー協会は、日本代表の戦力アップも大切なテーマです。Jリーグでいい選手を育ててもらい、欧州でブラッシュアップをさせる。そうした選手が、海外に出やすくなるのも2シーズン制のメリットでしょうか。もちろん伝統国が大切にする、1シーズンでの実力を測るという魅力が失われてしまうのは痛手です。細切れのシーズンでは、サッカー力そのものが育たない。シーズンを戦いきる実力を身につけてもらいたい。サポーターの批判も正当なものが少なくありません。
もう一度立ち返れば、今回のJリーグの2シーズン制は、シーズンを割る発想が先にあったわけではなくて、まずはサッカー協会が『このままじゃ日本代表がワールドカップに出られなくなってしまうよ』『このままだと外国に行った選手が疲れたままで世界と戦えなくなってしまうよ』『いくら頑張ったって準決勝以上に行けないですよ』というところから始まっていると見えるのです。
ラグビーもおそらく同じ循環があると思います。日本ラグビー協会が持つジャパンの実力がどうなのか。それがトップリーグにも大きく影響するはずなんです。トップリーグとジャパンとの間のスクラムが非常にうまく行っているのかどうかですよね。あるいは、若い世代の育成もそうですね。今、サッカーの世界では高校選手権の価値がものすごく落ちてしまっている。それはサッカー協会が中心になって始めた年代別のサッカーがすごく強くなったからです。ラグビー界は花園がどうなのか? そこから違う世代が展望としてあるのか? 野球界もここ数年U-18が画面上に出て来る時代になりましたよね。野球界でさえ、長い間拒否していたU18の世界に日本代表を送る時代になっているんです。その世界の中で若い世代をどう戦わせて、それが帰ってきたときに国内のリーグとどうタッグを組むかというところに、相当緻密な判断をし、あえて大胆なことをやっていけるかどうか。これは教育界を巻き込まないといけないですから、相当時間がかかると思うんですよね。
でも、日本のラグビーはインテレクチュアル(知的)なスポーツですし、やっている人たちの世界観が非常に高いので、私は全然不可能なことではないと思います。
あとは安全問題に対する対応ですね。親御さんたちの安全問題に対する対応がどうなのか。それをどういう風に克服するか、ですよね」
──2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京五輪をどのように市民として関わっていったらいいでしょうか?
山本教授「お立場とかお仕事とか、済んでいる地域とかにも関係があると思いますけど、まずは非常にたくさんの組織ができると思います。ボランティアの組織もそうですし、色々な自治体としての動きもありますし、そうしたものにどういった入り口があるのかをまずは探っていくことがひとつのポイントだと思います。
ラグビーの世界の方々にとって非常に幸せなことは、ラグビーW杯と五輪が続いて日本であることです。これは大変大きなことで、他の競技団体はこういうことはないんですね。そこに向けていろんなことを計画的にできる、おそらく唯一の団体だと思います。ラグビーの場合、五輪の前年に世界大会が日本全国で行われることは非常に大きなアドバンテージになります。つまり、ラグビーに携わった方はもう1年あとに、もう1回世界規模の大会に携われるチャンスがあるわけです。ノウハウ、経験をもって五輪に乗り込めるわけですから、私は大変大きなアドバンテージをもって前に進めるんじゃないかと、むしろうらやましく思っています
山本教授に聞く「2019年ラグビーW杯の理想の形は?」
山本教授「ラグビーW杯にとって非常に大きいのは、五輪でセブンズが行われるということで、ラグビーに対する情報が他の競技に対してうんと多くなる可能性があるということです。それは2019年もあるし、2020年もあるということからです。しかも、相手が世界だということ。そして、特にどちらも予選なしで出られることがラグビーにとってすごくいいことなんです。ラグビーの情報がたくさん出ることは自明で、確実なことなんです。
例えばホッケーにしてもハンドボールにしても、今必死なのは、予選なしで出られる世界大会がそこまでないことで苦しんでいるんです。つまり、五輪直前にハンドボールなりホッケーなりが出てきて、さあ活躍はどうなのかと言われるわけです。ところがラグビーの場合は、2019年がありますから、2019年の中で多くの人が情報、つまり選手の力、世界の力、ルール、そういったものをすべて知った上で2020年に行くわけですよね。その点で言うと、ラグビーだけが非常に大きなアドバンテージを持っている。決まった2019年があるために、2017年、18年にはある程度のことはみんな知っているわけです。
その中でW杯を迎えるわけですから、その点で大いに自信を持って、どんどん選手を召集合宿にたくさん集めて、ガンガンやったらいいと思います。また、いわゆる昔のレガシーの選手もどんどん出てくると思います。そういう人たちをフィーチャーするのも役割だと思います。メディアの側は、そういう意味で言いますと、昔のプレーヤーや昔の試合の掘り起こしを積極的にやると思ます。ラグビーはそれを継続的にできる大きな追い風を持っているわけです。
また、2019年の中枢に入りそうな選手たちを、すでに2015年、16年からメディアは追いかけ始めると思います。そういった選手を大事にすることも重要だと思います。さきほどの講演で例に出した“ちょっと吠える選手を切らずに、ラグビー界に残せるかどうか”ですよね。ラグビーって格闘技系のスポーツだから、その部分はすごく大事です。テクニックやスキルだけじゃなくて、ややもするとスキルだけに走っちゃうんですけど、ラグビー界は吠えるような選手の個性を大事にできるか、ラグビー界には他のスポーツに先駆けて見本を見せてもらいたいですね」
|