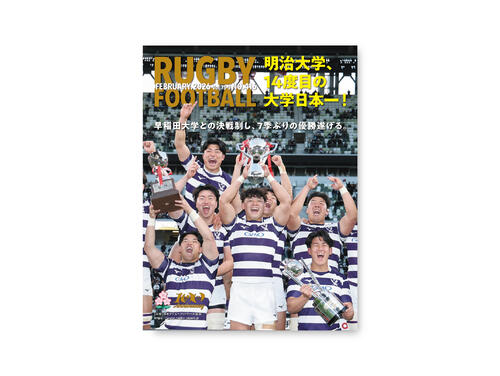|
佐藤真海が伝える“スポーツのチカラ”
皆が尊重し合える社会を残すために
公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団と日本ラグビーフットボール協会が主催する「みなとスポーツフォーラム 2019年ラグビーワールドカップ(W杯)に向けて」の第50回が1月21日、東京都・港区の「みなとパーク芝浦 男女平等参画センター(リーブラ)ホール」で開催された。
今回はアテネ・北京・ロンドンパラリンピックに出場し、2020年東京五輪・パラリンピック招致ではプレゼンターとしても活躍した走り幅跳びの佐藤真海氏を招き、スポーツアナウンサーの深山計氏の進行のもと「スポーツのチカラ」をテーマに講演が行われた。
■学生時代にガン発覚「まさか自分が」
|
![深山計氏、佐藤真海氏]()
![深山計氏、佐藤真海氏]()
|
|
|
深山計氏、佐藤真海氏
|
佐藤氏は宮城県気仙沼市で生まれ、小学生では水泳、中学生からは陸上競技に打ち込むスポーツ少女として育った。高校はスポーツの強豪・仙台育英高に進み、その後かねてから志望していた早稲田大へ。憧れだったチアリーディング部に所属し、大学生活を謳歌(おうか)していた。
しかし、間もなく20歳を迎えようかというころ、右足にねん挫に似た痛みを覚えるようになる。次第に「足が砕けるような痛み」へと変わり、病院で検査した結果、骨肉腫という骨のガンであることを宣告された。
「みんな他人事だと思うんですけど、私にとっても『まさか自分が』という感じでした」と当時を振り返った佐藤氏。右脚をひざ下から切断することを余儀なくされ、抗がん剤による副作用で髪の毛が抜けるなど苦しい時期を過ごした。
そんな中で支えとなったのが、同じく病と闘う仲間や、大好きな母親の存在だったという。特に母親から送られた「神様は、その人に乗り越えられない試練は与えないんだよ」という言葉は今や信念となっており、「どん底でダメな時にも『自分なら乗り越えられるぞ』という気持ちにさせてくれる」と明かした。
ガンを克服し無事に退院した佐藤氏だが、すぐに立ち直れたわけではなかった。「表に出さないまでも、ここから3年間くらいはやはり喪失感というものがあって、フラッシュバックのように急に悲しくなることがあった」。かつらを被り、慣れない義足で歩く自分を情けなく思い、泣き明かす日々だったと回想する。
泣いてばかりの自分が嫌で「わらにもすがる思いで」始めたのがスポーツだった。日本における義肢装具士の第一人者である臼井二美男氏と早くに出会ったことで、義足で歩くのと並行して再び陸上競技の世界へ。「スポーツをすると目標ができますよね。なので自分の嫌な部分を乗り越えるように前へ前へ、一歩一歩という気持ちになりました」。
スポーツを通じて自信を取り戻していった佐藤氏。パラリンピックから学んだことへと話題は移っていく。
■第2の人生が開いたアテネパラリンピック
司会・深山計氏(以下、[深山])「(陸上競技を始めて)『さあパラリンピックを目指そう』となりました」
佐藤真海氏(以下、[佐藤])「いつか行きたいというふうに最初のころは思っていましたね。すごい世界だろうなあと。それが自分が思っていたリハビリの延長ではなくて、これはスポーツの世界だというのを映画で見て。じゃあやるからにはいつか(パラリンピックの舞台に)立ちたいと」
[深山]「いつかは立ちたいと言いましたが、それをすぐに達成しました」
[佐藤]「2004年(のアテネパラリンピック)ですから(走り幅跳びを始めて)1年半ぐらいで。まだ本当にひとり赤ちゃんがいたようなレベルだったんですけれど、世界の標準記録を突破できて。でもトップは5メートルを跳んでいましたからね。(記録は)3メートル95という当時の自分には精いっぱいの自己ベストだったんですけれど、すごく世界を感じました。でも、この舞台に立てたことで私の第2の人生が開かれました。これがなかったら2回目も3回目もその後の(東京五輪の)招致活動などもないかなと。すごく刺激を受けて帰ってきました」
[深山]「そしてアテネの次は北京です」
[佐藤]「この大会どちらかと言うと、4年間かけて出場する難しさを感じた大会でした。アテネの時は知らないうちに世界の舞台にいたという感じでしたが、北京は4年間で強くなって戦いに行くんだという気持ちで、自分にプレッシャーをかけてしまいましたし。一方で仕事との両立がうまくいかなかったり、ケガをしたりということで苦戦した4年間でした」
[深山]「だけど、いろんな意味で反省も踏まえてロンドンに挑戦しました」
[佐藤]「もう一度チャレンジするのかということを考えた上で、『もう一回やってみよう』と思って、体をまず鍛え直そうと。後は4年間あるから踏切足を変えてみようと」
[深山]「踏切足を左右変えるということは、それまで健足側で跳んでいたのを義足のほうに替えるということですね」
[佐藤]「全然簡単なことではなくて、もちろん記録は落ちる一方でしたけれど、世界トップの潮流は義足踏切になっていたので。自分の脚で跳びたかったですし、正直自分の軸足が左だったので、左で跳びたいという気持ちはありました。でも、これをやらずに走り幅跳びをやめていいのかと思うと、やっぱり可能性があるのはもったいない、ダメだったら元に戻せばいいと思って」
[深山]「要するに強化とチャレンジですよね。義足で踏み切る練習をしていって、ロンドンを迎えたと。この時の感想は後で詳しく聞こうと思います」
■最終プレゼンに込めた思い
[深山]「2013年シーズンは世界選手権で表彰台に上ったり、招致活動で大変忙しいシーズンになりました」
[佐藤]「3月に東京にIOC(国際オリンピック委員会)の委員が視察に来るときにプレゼンテーションをしたのが最初でしたね。英語が流暢じゃなかったので本当に大変だったんですけれど、自分の自己紹介から東京のプランまで英語で話せるように覚えたり練習したりして臨みました。アスリートだから偉い人の陰に隠れてっていうこともできたと思うんですが、私とフェンシングの太田(雄貴)選手がメインでやっていて、自分たちが思い切ってやらないとアスリートのパッションが伝わらないわけですよね。なので、一回一回の機会をすごく大事にするよう意識するようにしました」
[深山]「そして(9月にアルゼンチン・ブエノスアイレスにて)最終プレゼンテーションを迎えるわけです。ここで主張したメッセージについて教えてください」
[佐藤]「パラリンピックを通じて、大切なものは私が失ったものではなくて、私が今持っているものであるということを、そのスピーチの中に込めました。4分間のスピーチというのが皆さんに共感していただけるものになったとしたら、一言たりともうそ・偽りはないというか、自分の心の中の思いと経験をすべて訴えた感じですね」
[深山]「だから人の心を打ったという。IPC(国際パラリンピック委員会)のフィリップ(・クレイバン)会長が後に、『日本人は感情を表すのが得意ではない。しかし、佐藤真海のプレゼンテーションは感動的で、IOC委員の気持ちを一気に引き寄せた』というふうに記者会見で語っていました」
[佐藤]「うれしいですね。確かにこのスピーチの練習は1週間しかなかったのですが、何をしていたかというと、恥ずかしさを捨てて覚え切る作業です。本番さながらにライトを受けてステージに立って話すというリハーサルを何度も繰り返し、その中で恥ずかしさを捨てていって、ものにしてったっていう」
[深山]「競技と一緒ですよ。本番に強いんだから」
[佐藤]「でもこの経験は初めてでしたし、競技で緊張して大崩れすることはなかったので、『この緊張は自分にとっていいものだ』と言い聞かせて考えましたね」
[深山]「まさにそれが“スポーツのチカラ”ということになりました」
■パラリンピック会場を満員にするためには?
[深山]「ロンドンパラリンピックで佐藤真海が感じたこととは?」
[佐藤]「ロンドンでは(観客が)純粋にスポーツを見に、応援しに来ていたんです。子どもたちが親の手を引っ張って連れてきて、選手の名前を呼んで応援している姿が見られました。多分、日本の子どもたちに、誰かパラリンピックの選手の名前を知っているか尋ねたら知らないですよね。それくらい、トップアスリートとして、オリンピアンとパラリンピアンが並んでいたという状況だったのかなと」
[深山]「ということは、急にそうなったわけではなくて、いろんな理由があったはずなんです。その1つが"Meet the Superhumans"というテレビCMです。これはイギリスの特徴ある編成をしている「Channel 4」という放送局でずいぶん放送されていたようですね」
[佐藤]「もう純粋にアスリートの肉体美というか力強さですよね。パラリンピックという要素に障害を持つことがありますが、それは例えば車のクラッシュ、戦争、妊婦さんのおなかの中のエコーという映像が一瞬一瞬に挟まれていました。まさか自分から障害を持つわけではないじゃないですか。私も含めて、ある日突然このような運命を受けて、それでも不安とか葛藤を吹っ切って前に進んでいくというのをシンプルに表していると思います。日本ではまだまだこういったものは見られないですよね。どうしても感動ストーリー、障害を乗り越えて頑張って走っていますみたいなところで終わっちゃうんです。なので、このように一歩上にステージを上げていかないと、この満員のスタジアムというのは日本ではできないのかなと思います」
パラリンピックに3大会出ましたけれど、ボランティアの存在感がすごい大きいんですね。ボランティアと言っても日本で持っていたイメージと違って、大会を作っている。イギリスの場合は「ゲームスメーカー」という呼び方をしていましたし、実際に大会を盛り上げて作っていく人たちという感じだったんです」
[深山]「ボランティアの応募が24万人いたというのがすごいですよね」
[佐藤]「そうなんですよ。日本もそのくらい応募があるといいですね。今、英語が話せなくても、5年間あれば日常会話くらいできるんじゃないかなと」
[深山]「みなとスポーツフォーラムは今日がちょうど50回で折り返しですが、目指すものは“見るスポーツ”、“するスポーツ”、“支えるスポーツ”と考えています。これはまさにね、こうやってみんなで支えていこうということではないでしょうか」
■佐藤氏「弱いからこそあえてチャレンジする」
休憩を挟んで行われた第2部では、第1部の講演に関する質疑応答が行われた。
──企業スポーツとして意識していることは?
[佐藤]「記録を伸ばすことだけで終わらせないということですね。やはり『やらせてもらっている』というのもありますし、夢に向かう素晴らしさや生き方を子どもたちにシェアしていくことなどを使命感を持ってやっています」
──特に復興支援はご自身の生まれ故郷でもあり、仕事を超えた使命がある?
[佐藤]「『支援』という押し付けがましいものではなく『伝えたい』という思いでやっています。それを継続できているのも会社の協力なしではできないですし、そこはうまくリンクしてできているという感じですよね。だから私の存在感も広がりますし、相乗効果かなと。10年経ってやっとお役に立てている感じがします。最初のころはお荷物だったのかなと思うんですけれど(笑)、それでも可能性が広がってきて、自分にしかできない活動をやってこられたと思います」
──佐藤さんのメンタル面の強さの支えは?
[佐藤]「強いと思ったことはそうそうなくて、弱いからこそあえてチャレンジを続けてきて、それが自分のベースになってきたのだと思います。何か2つ選択肢があったら難しいチャレンジを選んだり、安全パイの成長のないほうではなく、思い切ったチャレンジに飛び込めるようになったと思いますね。『自分の限界のふたを外す』と言っているのですが、『やってダメなら戻ればいいじゃん』と」
■さらに誇りに思える日本へ
──2020年東京パラリンピックで会場を満杯にするためには何が必要か?
[佐藤]「イギリスでの例がいいヒントになると思うんですけれど、スポーツ界だけでなくメディアやスポンサー企業など多くの皆さんの協力がないと、ああいうテレビ(CM)や、日々応援してもらう機会、見てもらう機会、触れ合う機会を作れないんじゃないかと思います。1回見たらやっぱりイメージが変わると思うんですよね。その1回をたくさん作っていかないといけません」
[深山]「いい例が去年、織田フィールド(東京・渋谷区)でやっていたブラインドサッカー。あれはびっくりしましたね。初めて見たんですけれど、声を出して応援したら怒られてしまって」
[佐藤]「そういうのが分からないと。2020年に「シーッ!」とか言われてもね(笑)」
──東京五輪の10年後の2030年に日本はどうなっていると思うか?
[深山]「60歳を境に『後もう何年もないな』となったところで、実際問題、自分はどうやって生活していけるのか、これまでは階段をひょひょっと上がってきましたが、『こんなのひょっと上がれるのか?』ということを普通に考えるようになりました。佐藤さんと仕事で関わらせてもらうようになってから、ともに生きる、共生するということを難しく考えないで、『階段を上れるかな』といったことを自分が当事者になった気持ちで考えることができるようになる社会になればいいと思いますし、その時には自分はそうだと思います。『目の不自由な方はこうですよ、お年寄りはこうですよ』といちいち言わなくても普通にね。そして『2020年のレガシーはこういうところにあったね』となればいいと思います」
[佐藤]「2030年は世界が近くなっているといいなと思います。日本は島国なので、どうしても“普通”から外れる人を特別視してしまうというのが、正直あるのかなと。自分がパラリンピック選手になったり、海外に行って文化や人種の違いを感じながらいろんなことを見てきたりするなかで、本当に自分の世界が広がったなと感じるんですね。2019年のラグビーW杯は全国に広がる、2020年もかなり大きな大会として迎えるということで、まず子どもたちの視野がグローバルに広がると思いますね。また2020年に向けて、一人一人の底力を含めてすごくレベルアップをしていく、企業も技術開発したりと世界に誇れるものを作っていくと。それが集結していって2020年を迎えて、さらに10年経って、さらに誇りに思える日本になっているんじゃないかなと期待しています」
[深山]「日本で開催された一番近い五輪は長野、その前が札幌でその前が東京です。五輪の後のことを考えようということはこれまでなかったと思うんですよね。今はそれをやらないとダメよ、と。お金の無駄遣いしてもしょうがないし、考え方もそうじゃないですか。そういったことを今、ここで話をしたり皆さんが考えられたりするというのがあるので、今回はすごく期待できるんじゃないですか」
[佐藤]「この5年間をどう過ごしていくかが一番大事かなと思いますね」
あなたにとってラグビーとは?
[佐藤]「生での観戦が大好きです、という感じですね。テレビで見るよりも人間がぶつかり合う音を生で聞くのがすごく好きで「これぞスポーツ」という感じがしています」
[深山]「高校ラグビーや大学選手権や、サントリーと明治大学の日本選手権までは中継をやっていたんですよ。仕事で携わっていたので、競技として面白かったですね。方式が変わってから四半世紀経ちますが、ラグビーでよく言われるのはノーサイドの精神で、それもありますが、僕は戦略性や組み立てがすごく面白いなと思います。皆さん、もっとラグビー場に行きましょう!」
|